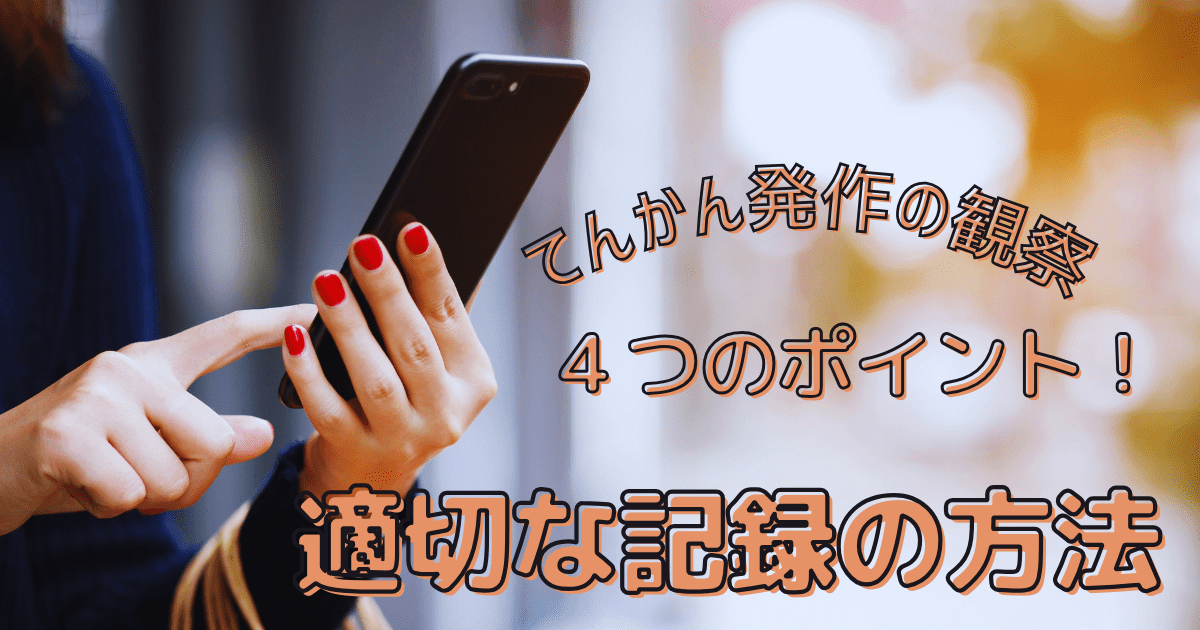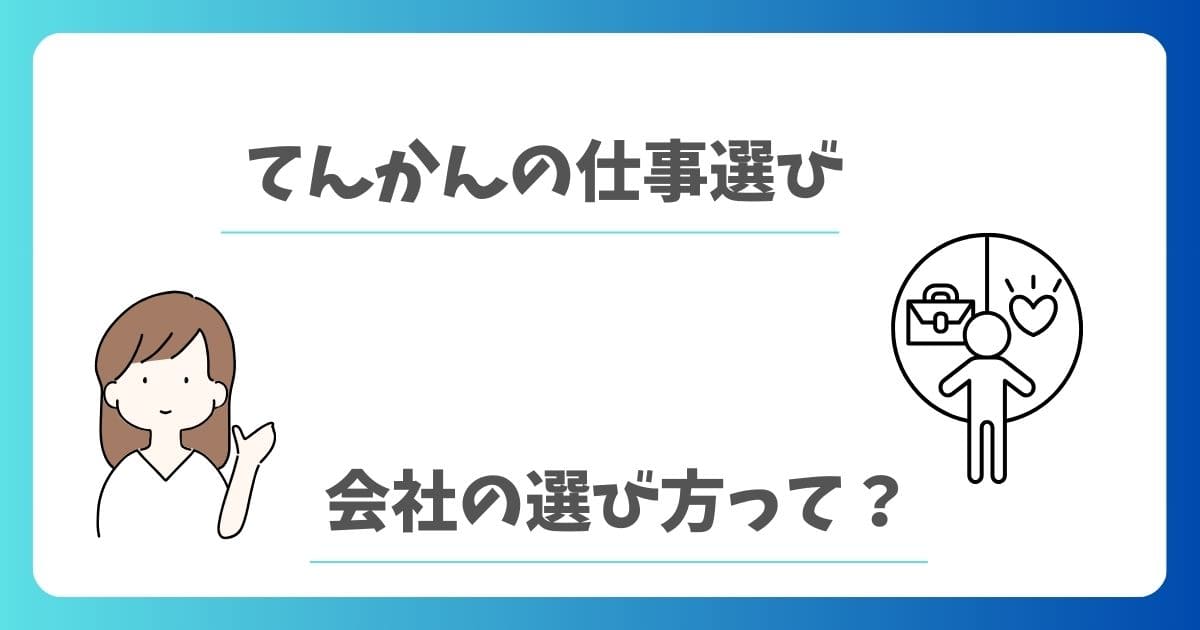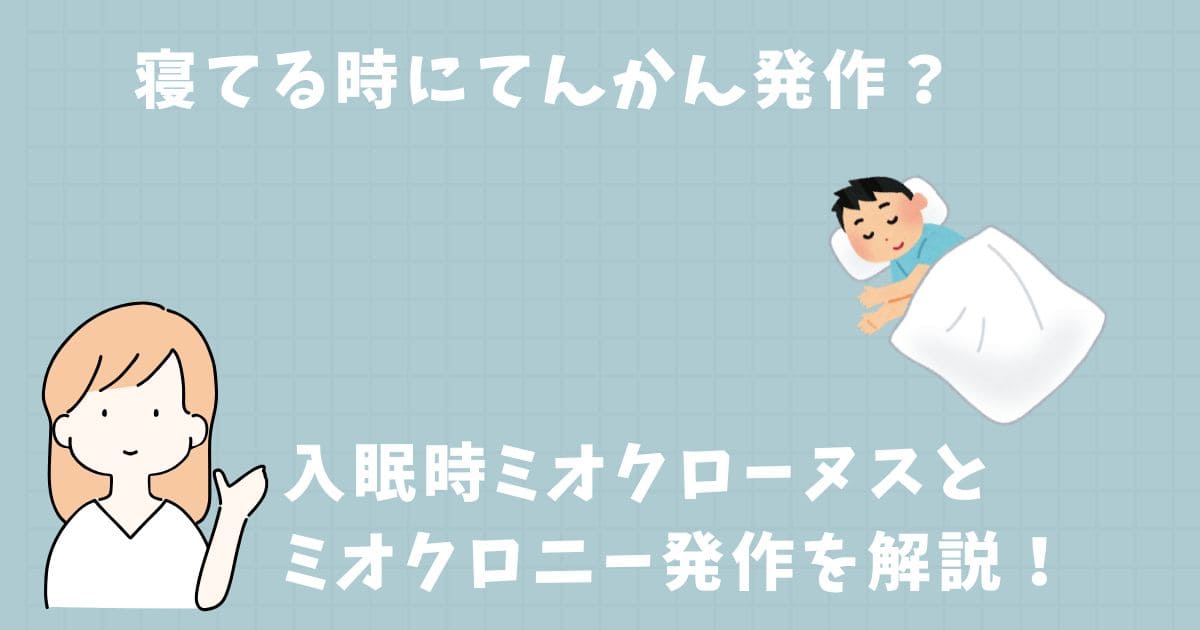
早く寝たのに、決まっておなじ時間に、目が覚めて発作が出て熟睡できなく寝不足で、昼に眠気が襲ってきた経験ありますよね。寝ている時に目を覚ました後に、てんかん発作がある人は、寝るまえや起きてすぐに、体がぴくつく・けいれんを伴う発作入眠時ミオクローヌスとミオクロニー発作があります。
寝るまえや起き上がってすぐに、てんかん発作が理由は、どちらも、交感神経と副交感神経が関係しています。
そして、寝てから、てんかん発作を理由は、ノンレム睡眠とレム睡眠が関係していると考えです。
ノンレム睡眠とレム睡眠は、一時間半から二時間の周期で切り替わる時に、急にパッと目が覚めて発作を起こす事があります。
筆者は、中学生から高校二年ころまで、はやく寝ても、疲れないように気をつけていても、ほぼおなじ時間にてんかん発作を起こして、よく昼に眠気があり授業中にばれないように寝ていました。
今回は、寝てる時にてんかん発作!?入眠時ミオクローヌスとミオクロニー発作について解説します。
寝入りばなの「ビクッ!」は大丈夫?多くの人が経験する入眠時ミオクローヌス
布団の中で突然、体が一瞬跳ね上がるような感覚。ドキッとして目が覚めてしまう…そんな経験ありませんか?
これは多くの人が経験する入眠時ミオクローヌスという現象です。
脳が睡眠モードに切り替わる際に起こる生理的な反応で、通常は心配いりません。
しかし、頻繁に起こる場合や、日常生活に支障がある場合は、睡眠専門医に相談してみるのも良いでしょう。カフェインやアルコール、激しい運動は誘因となることがありますので、寝る前は避けるのがおすすめです。リラックスできる環境を取り入れることも有効です。
それって心配なやつ?多くの人が体験するジャーキングとは?
入眠時のビクッ!実は多くの人が経験する生理現象で、疲れている時などに起こりやすいです。
ジャーキングは、寝入りばなに体が 突然ビクッとなる現象です。高い所から落ちるような感覚や、 電気的な刺激を感じることがあります。
これは「入眠時ミオクローヌス」とも呼ばれ、健康な人でもよく起こります。疲労やストレスが原因となることが多いですが、基本的には心配いりません。ただし、頻繁に繰り返される場合は、睡眠障害やてんかんを疑う場合があります。
気になる場合は医師に相談してみましょう。
私のはどっち?入眠時ミオクローヌスによくある3つの特徴!
基本は放置でOK!でも「頻繁すぎるかも…」と感じたら?
基本は様子見でOK。ただし、睡眠不足になるほど頻繁なら、専門医への相談も検討しましょう。
入眠時ミオクローヌスは生理的な現象ですが、もし「最近頻繁すぎるかも…」と感じた時は、自己判断せずに一度専門医に相談してみることをお勧めします。
とくに、夜中に何度も目が覚めてしまう、日常生活に支障が出ているといった場合は、医療機関の受診を検討してください。相談は、脳神経内科や精神科などが専門となります。医師に症状を詳しく伝えることで、適切なアドバイスや検査を受けるようにしましょう。
ただの寝相じゃないかも?見逃したくないミオクロニー発作との違い!
寝入り際のピクッは生理現象。でも、時間や強さによっては発作の違いを知っておきましょう!
入眠時ミオクローヌスとミオクロニー発作はどちらも筋肉が 突然収縮する現象ですが、重要な違いがあります。入眠時ミオクローヌスは、寝入りばなの浅い睡眠時に単発で起こることがありますが、配いりません。
一方、ミオクロニー発作は、睡眠中だけでなく、起きている時にも起こります。また、連続して起こったり、より強く体を動かしたりすることがあります。
意識がなくなる、繰り返される、日常生活に支障があるなどの場合は、てんかんの可能性も考えられるため、くり返し体がぴくつく場合は、医療機関を受診しましょう。
「ピクピク」が繰り返す…?知っておきたい「てんかん発作」
同じ動きが続く「ピクピク」は、てんかん発作の可能性も。どんな種類があるか、詳しく見ていきましょう。
「ピクピク」と体が繰り返して動く場合、それはてんかんsかもしれません。てんかん発作には様々な種類があり、一部分だけがピクつくものもあれば、全身が リズミカルに 動くものもあります。

ミオクロニー発作っていうもの?

そうだね。
ミオクロニー発作には、ミオクロニー欠神発作やミオクロニー脱力発作、若年ミオクロニー発作など、年齢や症状で名前がちがうことがあります。発症年齢は10代から20代と幅がありますが、声変わり時などホルモンバランスが変わる思春期に多いです。症状や原因については、むずかしすぎて割愛させてもらいます。
詳しく知りたい方は、「ミオクロニー発作、原因、症状」などで、検索してください。または、以下からも確認できます。

ホームページは、表の173・174をみてね
たとえば、、ミオクロニー発作は、一瞬、 電気ショックを受けたかのように、体がビクッとなるのが特徴です。また、間代発作では、手足などが 一定のリズムでガクガクと動きます。体のこわばりもある強直間代発作もあります。
意識がある状態で体の一部がピクピクする場合は、単純部分発作の可能性もあります。これらの症状が見られた場合は、自己判断せずに、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
似ているけどココが違う!見分け方の3つの重要ポイント!
似ている入眠時のピクッ。発作との違いは?3つのポイントでしっかり見分けましょう。
入眠時ミオクローヌスとミオクロニー発作は見た目が似ていますが、見分けるための重要なポイントが3つあります。
まず、起こるタイミングです。入眠時ミオクローヌスは、寝入りばなのウトウトしている時や朝起きてすぐだったり、一時間後に起こります。
ミオクロニー発作は、睡眠中はもちろん、昼間にも起こる可能性があります。次に、頻度とパターンです。入眠時ミオクローヌスは単発で終わることがほとんどですが、ミオクロニー発作は連続して起こったり、時間をおいて繰り返したりすることがあります。
最後に症状です。入眠時ミオクローヌスでは通常、意識の変化やその他の症状は見られませんが、ミオクロニー発作の場合、意識がなくなる、体が硬直する、倒れるなどの症状を伴うことがあります。ポイントを意識することで、区別がつきやすくなります。
医者にどう伝える?診断に役立つ「観察記録」のつけ方【動画も有効!】
正確な診断には記録が重要!いつ、どんな風に?動画も有効活用して、医師に伝えましょう。
医師に「ピクピク」について伝える際、 詳細な観察記録は非常に役立ちます。記録するべき項目は以下の通りです。
スマートフォンの動画などで様子を記録するのも非常に有効です。言葉だけでは伝わりにくい細かな動きや様子を医師に直接見てもらうことができます。記録した動画は消去せずに、受診時に医師に見せるようにしましょう。
まずはセルフケア!睡眠の質を高めてピクつきを減らす生活習慣☆
質の良い睡眠はピクつき軽減の第一歩!今日からできる生活習慣を見直して、快適な眠りを手に入れましょう。
寝入り際のピクつきを減らには、睡眠の質を高める生活習慣を意識することが大切です。まずは、毎日決まった時間に寝起きするように心がけ、体内時計を整えましょう。
寝る前には、カフェインやアルコールの摂取は避け、リラックスできるような入浴や読書などの習慣を取り入れるのがおすすめです。
寝室の環境も重要で、暗く、静かで、快適な温度に保つようにしましょう。日中は適度な運動をすることも質の良い睡眠につながりますが、激しい運動は寝る直前は避けるようにしてください。
また、寝る前にスマートフォンやパソコンなどの画面を見るのは避け、リラックスした状態で眠りにつけるように工夫しましょう。これらの生活習慣を実践することで、ピクつきの軽減が期待できます。
てんかんに限らず、よく寝て適度な運動しましょう。はじめは、焦らずゆっくり気をつけることが大切です。
睡眠中の「ビクッ」正しい知識で不安を解消しよう!
睡眠中のビクッは多くが生理現象。ただし、注意すべきサインもあります。正しく知って不安解消しましょう!
睡眠中に起こる「ビクッ」という動きは、多くの人が経験する入眠時ミオクローヌスは、生理現象なので、過度に心配する必要はありません。
寝るまえや起きてすぐは、脳が睡眠状態へ移行する際に起こる自然な反応です。しかし、もしその「ビクッ」が頻繁に起こる、睡眠中だけでなく日中にも起こる、意識を失う、体の一部が強くけいれんするなど、いつもと違うと感じる場合は、念のため医療機関を受診しましょう。正しい知識を持つことで、安心して眠りにつけるようにしましょう。

さいごまで読んでくれてありがとう。